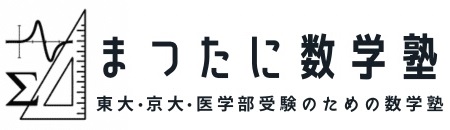英文を人が書いてるか機械が書いてるか区別つかなくないか。。
松谷です。
ちょっと英語の長文を書く機会があったのですが、書き始めてから、しばらくして、ふと途中でストップしたんですね。
それで、日本語で内容をサーっと書いたものをchatgptに翻訳させて見たら、20秒ほどで、なんとちょうどよい素敵な英文。
少し僕の意図と違うところを直したら、あっ、完成。
あれっ、これ、英文を人が書いてるか、AIが書いてるか区別つかなくない?
ごくごく自然なありふれた英文の文体になってるもの。内容は僕が言いたいことのうえで。
うーん。これは、、
スタンドアローンで何もつながってない状態で、入試会場で英作する意義ってなんなんだと思わされますね。。
以前、大学生のレポートなどをchatgptで書いたものか判断してチェックするみたいなニュースを聞いたことがあったんですが、少なくとも英文(今回はビジネス文書)については、僕にはこれが人の文かchatgptが書いた文かまったくわからない。。
英語学習はコミュニケーションしたりするための楽しさだけが残るのか?はて。
ちなみに、僕は大学教授の論文の英文チェックの負荷が劇的に減ったんじゃないかと思うんです。
まったく教授の本分じゃないですもの。学生の理系の研究論文の英語のチェックなんて。
うーん、考えさせられますね。
A Iといえば、共通テストの点数でついに9割を超えて91%になって、東大のボーダーを超えたというのが話題です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f6d0f823bd132948fa218be7c1b932a94c714453
https://note.com/lifeprompt/n/n02c40e908130
残りは多分日本では理三と京医と科学大の後期くらいですかね。
まあ、それも時間の問題でしょう。多分1年とかでしょう。
ふーむ、こちらもこちらで、学力試験をどういうものにするべきかというのを問いかけられてる感じがしますね。
一足先に、将棋の棋士などの世界に起こっていたことが、ついに全体に波及してきましたね。
医師国家試験や司法試験なども平均的な突破レベルは既にあるらしいですからね。
ふむ。まあ、便利に楽に学べるようになって楽しそうな感じはしますが、過渡期においてはなかなか対応が分かれてしまいそうですね。