課題を感じたことにアクションを促したり。それでも最後は自分次第。
松谷です。
小さい塾ですから、できたらみんな上手く行って欲しいわけですよ。
だから、課題を感じた子たちには何らかのアクションを促したりして、変化を求めたりします。
そのアクションを求めるときの僕の言動が多少強めにでてしまい、塾を辞められた方もいます。
まあ僕も加減とか良くわからないんでね。。。
怒るときは怒るし、励ますときは励ますし、厳しいことを冷静にいうときは冷静にいうし、、という感じです。
割と全部正直な感情ではあります。
でも、まあこのまま放置したらだめな流れしかみえなかったら、
なんとか流れを反転するためのきっかけが必要な気もするんですよ。
そのきっかけになれたらラッキーだなって。
でも、例えばこちらがアクションを促したとしても、実際に最後の変化をするかどうかっていうのは自分自身の決定なんですよね。
馬を水飲み場に連れていくことはできたとしても、水を飲むかどうかは馬次第ですからね。
ましてや、人については水飲み場に連れて行くことさえも正直なかなか難しい。
水飲み場があそこにあるよといっても、水飲み場に行かない人もいるわけですね。
それで餓死しそうになっているんですけど、餓死しそうになっている自分に気づかないと。
なんとか水飲み場への道を一方通行にして、後ろからつぶされかねない岩とともに急き立てる。
これで水飲み場に行くかもしれませんね。でも、やっぱり最後に水飲み場で飲むかどうかは自分次第ですね。
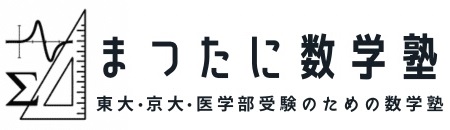



いつもお世話になります。先生は、子供の勉強をいつまで親が見守るべきだと思いますか?
先日、中1の息子と同じ学校のお母さん達と話をしていて、中には、学校でやっている勉強の内容を全部の科目把握しており、定期テストに備えるために最低何回回す、この科目はプリントだけでは不十分なので参考書はこれが良い、など知識を伝授していただいたんですけど、すごいと圧倒されるとともに、いつまで親はそのような管理をしないといけないんだろうかと考え込んでしまいました。
馬の話ですが、いくら親が参考書を買い揃えてもやるのは子供なので、いつか自走してくれないと、中学受験の時のようなサポートをするのは精神的にも疲れます。
その方のようなスーパーマザーの話を聞き、逆に焦ってしまったので、今日のブログの話と少し関連する気がして聞かせていただきました。
できれば、私もサポートできる親でありたいと思いますが、親はいつまでどこまですればいいのか、参考までに先生の意見を聞かせて下さい。
いろんな考えがありますよね。
某有名ママみたいな徹底的サポート型もありますしね。
でも、受験はまだしも、学校のものまで徹底管理って現実的に無理なんじゃないですかね。。副教科もありますし。。できたとしても、続かないというか。大学でもやるんですか?って感じですしね。
中1の最初は少しサポートしてあげて、ある程度コツがつかめたら、どこかで手を離して自分でやるように仕向けてあげたらいいんじゃないでしょうかね。適当に塾とか塾の自習室にアウトソースできるところはアウトソースして。
で、自分でやり出したりして、うまくいってるときには見守って何か苦労しそうとか苦労してるときとかは割と早めに話を聞いて相談にのってあげるというのでいいんじゃないでしょうか。
なんとなく友達の影響も受けてある程度勉強はこれくらいしなきゃなみたいなことを感じたりもするかなとは思います。これくらいの順位にはなんとなくいたいなみたいな心理も働くかもしれません。
ありがとうございます。
数学しか塾にいってないし、学校の勉強はダイニングテーブルでやっているのですが、私はちらっと料理しながら横目で見る程度です。
お任せしております。
社会など暗記科目は中学受験の時一緒にやった覚えがありますが、いつまでもあんな事一緒にしたくないというのが本音で、でもやっているお母さんがいるんだったら、子供が悪い成績取ってきたら一部親の責任のような気もしそうです。
先生の話を聞き、もうしばらくは暗記科目については付き合おうかと思いました。
せめて、テスト前だけでも。
ぼんやりした質問に答えていただき、ありがとうございました。