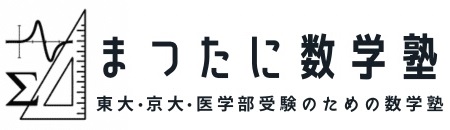なぜ洛南小では中学受験の問題を小4~6の間させるのですか?
松谷です。
なぜ、洛南小では、中学受験用の問題を小4~小6の間にさせるのですか?
(受験もないのに。もしくは、形だけの受験しかしないのに。)
という疑問を持たれた方が知り合いの方いましたので、
これは僕の多少の経験をもとにした憶測に過ぎないのですが、ちょっと書いてみたいと思います。
(たぶん学校説明会で直接聞いたら良かったですね!僕も先生方の考えを知りたいですね!!答えを知っている人いたら教えて欲しいです!!)
以下は僕の憶測を書いておきます。
洛南小自体は昔は全員に対して中学数学をどんどん進めるというカリキュラムをとっていたと思います。
元々洛南高校の高校数学の先生が下りてきて初代校長を務められたと思いますので、算数数学教育にはかなり思い入れがあったと思います。
しかし、これは僕も経験したのですが、たいていのケースでは、このカリキュラムはうまくいきません。
普通の公立の小学校くらいのカリキュラムの小6までの算数を、小3の学年終わりくらいまでに終わらせることは割と幅広いお子さんにとって結構な確率でできる可能性が高いです。算数は具体的で生活に密着していますし、そこまで難しいことをしていないので、上手くいきやすいです。親御さんが熱心ならなおさらでしょう。
一方で中学数学のようなちょっと抽象性が上がることをさせると、とたんに一部の生徒にとって難しいと感じるケース増えます。これはすごく増えます。ですので、これを学校全体で押し進めるというのは難しくなるんですね。
(抽象性が上がる内容を難しい内容の意味には踏み込まず計算の手続きだけに収めることにして誰でも進める可能性があるようにして、学習習慣の育成と計算のスピードと正確性の定着のみに特化したのがくもんの特徴ですよね。)
しかも、苦手な子が難しいと感じることだけが障壁じゃないんです。
それだけでなく、中学数学に入ると、得意な子にとっても、つまらないと感じるケースが増えるのです。
そこがやっかいなんです。
抽象性が高まった中学数学を手続きだけ覚えてやることに対しては、なかなか面白いと感じることができない小学生はめちゃくちゃいるんですね。これはかなりかなり算数が得意な子でもです。(もちろん気にせず進められる子もいますが)
そう考えると、低学年から学校全体として中学数学を進めていくことは茨の道すぎて不可能なんですね。
では、中学数学にどんどんと進めることができないとしたら、仕方ないなあ、どうしよかと。
あきらめて具体性のある算数の問題で多少の思考訓練をしながら、そのときがくるのを待つかと。
もう中学数学に進める準備が整っている人がいたとしても、いろいろな人がいるから、1周、2周、3周としておけばだいたいの子が準備が整うだろうと。中学数学については、学校では小6の後半くらいから少しだけ正負の計算と文字式とちょっとくらいの中学数学やるくらいでいいだろうと。
しかも、結局中学受験組の子が中学受験をしてくるわけだから、知識的な差もある程度最小化できますしね。
そんな状況なのかなと推測しています。
以上が僕の憶測です。
ちなみに、このような中学数学をどんどんやる方針から中学受験算数を主にやる方向への変化はこれで良かったのだと思います。僕としては学校としてとる変化としてはこれしかないというか。というかこれじゃないとより多くの生徒がもう小5くらいで本当に立ち行かなくなってしまって、学校の先生もそれをどうすることもできなくて、本当に苦しかったんじゃないかと思いますので。だから、さすがの変化の早い学校らしく、損切りをすぐにしたのかなと。
ちなみに、洛南は学力試験慣れしてない内部進学の生徒が結構いることを見越して、高校入学時点で上下にクラス分けをしているらしいですが、内部進学の子90人中15人くらい?は上のクラスにいるそうです。まあ、そんなにおかしくもない割合なのかなと。本当に無駄な教育を施してるなら5人くらいとかのはずなのでね。
小学校から進学の生徒で上のクラスのトップから下のクラスの中上位?くらいまでの生徒さんを割と多くのサンプルで知ってますが、結局その子のポテンシャルに応じて徐々になるようになっていくのかしらと感じてはいます。僕が下のクラスの半分以下くらいの実情を中学生以上の生徒では見れていないので、そのあたりの解像度が低い可能性はありますが。。。ただ、高校での模試の学年全体の平均点はだいぶいい(堀川とか洛星とかよりはちょっと良い?東大寺とかにちょっと足りないくらい?)ので、上下のクラスがいっぱいあるのに、全体としてある程度保てていることがすごいなと思ったりしています。良く知らないですが、330人くらいって多分全部なのかな。高校入学組を除いてるのかな。
ここからは、僕の実際に教えている体験ベースの感覚の話を書いておきます。
実際指導している感触としては、中学数学に移っていいタイミングは、ある程度得意な子だとして、個人差はありますが、小4はじめ~小5終わりくらいのどこかのタイミングで訪れます。なんというんでしょうか。頭の受け入れ準備が整うという感じです。
だから、僕が小学生を教える場合は、それぞれがそのタイミングが来るのを待っているんですね。
小4くらいまでの生徒が小学生の算数を終わった場合は、中学受験の算数をちょっとだけはさんでいます。難関校の難しい問題とかではなく、標準的な入試レベルのやつです。これは2~6ヶ月くらいかかるだけのものなのですが、これは意図的に中学数学に入るのを遅らせるために導入しているんですね。これに時間がかかっているなら、頭が準備できていないという証拠なので、意図的な延長措置として大いに機能しているという感じがしますし、これさえもさっと終わらせられるなら、まあ中学数学に入る準備が早めに整っている珍しめの生徒なのかなと。
僕の見立てはそんな感じで、そんな意図で進めています。
いずれにせよ小学生とか中1くらいまでは楽しむことが最優先なのかなと思うんですね。中学受験は勝負の世界だから別ですけど、中学受験を念頭に置かないなら、学習自体を興味を持って楽しめるという状況が一番いいなと思っています。