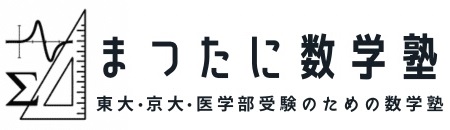定期テストの数学の答案が模範解答より素敵だったなあ!
松谷です。
このまえ少し定期テストの数学のテストが100点でしたって見せてくれた高校生がいたんですね。
高校の後半くらいになると100点をとること自体も立派だと思うんですが、それより感心したことがあったんですね。
それは、一つの大問の答案が模範解答より洗練されていたことですね!
模範解答はやや代数的にごり押しして三角関数と図形と方程式を用いて解いていたのですが(それはそれで重要ですが)、
その生徒の答案はベクトルの式の意味を解釈して、図形的な意味を読み取り、そこから答案にしていたんですね。
いやあ。素敵な答案だったなあ。
受験くらいで扱う問題になると、そろそろ一つの解答に限らないということが起こってきます。
そういう問題に相対したときは、これまで学んできたことをいろいろ組み合わせたり、アレンジしたりして自分なりの最適解を導きだしていくわけですね。
受験ということを考えると、解答スピードや、解答の再現性や、正確にできるか、思いつけるか、などなどを考慮しつつ自分なりの最善手を選らんんでいくわけですが、そこに少し個性が現れたりするわけです。
これは、基本を瞬時に取り出せる人が工夫しだせる領域で、ちょうど受験の数学の問題を解く醍醐味でもあります。
自分の武器を工夫して使って敵をどうやって倒そうかと考えて、攻略法を自分なりに見つけるところが面白いんですよね。
基本が出来ていない人は結局ここまでいかないので、基本とほぼ同じ問題についてだけ、なんとかぎりぎり解き方を思い出しながら適用して終わりという感じになります。それでは、そんなに面白くもないし、それでは、残念ながらレベルの高いところは狙えないんですよね。
演習1の生徒などは(もちろん数2Bや数3Cもではありますが)、授業で扱ったり、家で復習したりする基本の理解と出力の出来不出来が、自分のレベルの限界を規定しまいうる重要な事項なんだということに思いを持って行ってほしいなと思います。
というか、そこを本当の意味で意識できるかどうかが分かれ道なんだと思います。高2以下の演習1の生徒でそのことがつかめたうえで身についている人は現時点では、まだほとんどいません。1人、多く見積もっても2,3人くらいかなと。
残りの5カ月ではありますが、意識が変われば一気に10人くらいそのレベルになってもおかしくないと感じています。この5カ月が受験の成否すらも決めかねてしまうなとも思いますので、意識高く臨んで欲しいなと。
もちろん僕はこういうことって生徒に言っているんですね。でも、これはこちらが口でいくら言っても通じなかったりするんです。こればっかりは自分の意識なのでね。
そして実力があまりにも不十分な場合は、理系の場合だとして、実際には、演習2に行かせてあげることができないので、そうすると現実的には、東大理系京大理系上位医学部などは確率的にかなり厳しくなるかなと思います。クラスの判断は冷静に行うようにしています。実力不足だとクラス受講しても無意味なのでね。
今の自分の意識と行動が自分の未来を決めているんですね。
そして、それはあとで後悔しても結局取り返せなかったりするんですよね。