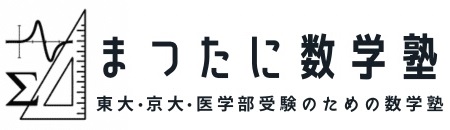2025合格体験記その10
松谷です。
京大農学部に合格したM.Kさんから合格体験記が届きました!!
彼女とは中1くらいからの付き合いですが、ひょうひょうとした女性なんですが、実はうちに秘めた芯が強いところもある子なんですね。正直、成績がまったく余裕だったわけではないなかで、高2の終わりから高3頭の受験の大事な時に海外留学にいったときはどうしようかと思いましたが、、、それでも彼女がやりたいということだったので、そのあと頑張れたんだろうなと。
彼女の中にきらりと光るものは感じていたのですが、しかしながら、途中の成績が結構厳しい時期もあって、いろいろな緊急対応策を相談したりしながら提案したりしていました。しかし、塾での数学の成績も模試も途中まで結構厳しく、、、、
しかし、直前演習の最後の2回くらいに、もしかしてここにきて合格ラインの数学得点に滑りこめるかもしれない?!という感触が。
最後にやりきってどうやって本番に間に合わせたのか?!どうぞ!!!
京都大学 農学部 資源生物科学科 M.K. 洛北
私は、中1の秋から松谷先生にお世話になりました。私は、もともと数学が苦手で好きでもなかったので、高2までは塾にとりあえず通っている感じで、数学は学校でも塾でもできていない方に入っていました。塾の予習も、学校の授業中の内職とバスの中でしていて、今から考えると数学の成績が伸びなかったのも当然だったなと思います。松谷先生からもチクリと嫌味を言われることも多かったのですが、なぜかやる気が出ませんでした。さすがに高3になってからは、勉強時間も増えて、数学にもちゃんと取り組むようになったのですが、それで今までの怠惰を取り返せるはずもなく、演習2では結構な確率でドベでした。しかし、英語と国語が得意だったため、夏の冠模試では、B判定をとることができ、数学が200点中33点でもなんとかなるんやと思い、英語で生きていくことを決意したのですが、秋の冠模試は、英語が大ゴケし、オープンD判定、実戦E判定を取ってしまいました。(悪すぎて、実は先生にも言っていない) 親にも京大は諦めろと何度も言われたのですが、先生が説得してくださったおかげで、京大志望は辞めずに済みました。結果、京大に受かることができたので、本当に松谷先生には、感謝してもしきれません。
ギリギリ合格できた要因を私なりに考えてみたのですが、一つには得意教科を作っていたこと、もう一つには共通テストで成功したことがあると思います。(あと、受験は結構運の部分も大きい気がします。)私は、英語を高3に上がるまでにある程度仕上げていて、秋模試では失敗してしまったのですが、英語の成績は安定していたと思います。よく言われることですが、どの教科でもいいので、ある程度自信が持てる教科を作っておくべきです。また、共通テストに関しては、京大志望の人は、足切りに引っかからない程度で良いと考える人が多いのですが、二次に自信がない人は、共テでしっかり取っておく方が良いです。農学部は第六志望まで書けるのですが、実際、私は、第一志望の食品と第二の応生はすべっているので、共テを取っていなかったら本当に危なかったです。また、出願を迷ったり、足切りに不安にならないためにも、目標点数は高めに設定しておいた方が良いと思います。
先生から、まつたに塾の宣伝もしろと言われているので、ここからはまつたに塾の良いところを書きます。まず、授業に関してです。1クラスが多くても15人くらいなので、先生に自分の答案を見てもう機会が多く、自然と答案を書く力がつきます。また、演習では講義というより、自分で解いていく方がメインなので、考える力も授業中に養えます。次に、先生自身についてです。先生はよく相談に乗ってくださいました。私は、計画を立てるのが苦手なので、どの教材を、どれくらい、いつまでにやるのかというのを、一緒に考えてもらっていました。今から考えると、私は高3の最初の時点で、だいぶ周りと比べて遅れていて、やるべきことが多かったので、自分1人で考えて、学習を進めていたら、正直間に合っていなかったと思います。本当に先生にはお世話になったので、合格発表の前は、落ちたら合わせる顔がないと思い、怖かったです。先生がいなかったら、本当に合格出来なかったです。松谷先生、長い間お世話になりました。ありがとうございました!!
ギリギリ合格へのすすめ
私は、高3の最初の時点で、京大合格からはほど遠く、高3の一年でかなり上げた気がします。この一年に関しては、誰に対しても胸を張って言えるくらい勉強しました。勉強時間はかなり多かったのですが、それでもなぜか時間がなかったので、最低限のことしかできていません。役に立つかわからないですが、私がどの時期に何をやっていたかを最後に書いておきたいと思います。本当にギリギリ間に合った感じなので、どの教材も私より早めにしておいた方が安心だと思います。
数学
6月までは、塾の予習復習と学校で配られた「理系数学入試の核心標準編」しかやっていなかった。この核心は解説があんまりで、問題も偏っているから、自分で買ってやるほどではない。私は全然チャートとかフォーカスゴールドとかは、やらなかったけれど、どう考えても春の間に基礎をやるべきだった。7月から9月は、流石に数学が酷すぎると気づき、理系プラチカをやった。簡単なようで、数学が苦手な人は結構詰まると思う。数学に苦手意識がある人は絶対に夏までにやるべき。10月は一対一の数3、数Cの例題だけをやった。数3Cは、習うのが遅いこともあり、演習量が少ないので、知識が定着していない人も多いと思う。時間に余裕がある人は、チャートやフォーカスゴールド、時間がない人は一対一を絶対にするべき。これも理想は夏中に終わらせるべきだと思う。11月からは「世界一わかりやすい京大の理系数学合格講座」という京大の過去問が100問載った本をやった。これはめちゃくちゃわかりやすく、問題の系統に合わせて頭の使い方が学べるので、京大志望は全員やるべき。この一冊をやってから、ごちゃごちゃしていた数学の知識がまとまって、実際に使えるようになった気がする。私は一周をとりあえず12月末までに終わらして、二周目を共テ終わりから一月末くらいまでに終わらした。周りでは、夏くらいから始めている人が多く、夏から始めていると、冠模試で点に繋がって、自信もつくと思う。共テ数学の勉強は、駿台の冬期講習と過去問を4年分、パワーマックスをやった。過去問は共通テストになってからの分だけで十分で、難化した場合に備えて、パワーマックスなど難しめの予想問題集をやることをお勧めする。共テが終わり、2月からは、6問の時間の配分の練習として、青本を8年分くらいと、塾の直前演習、苦手分野のプリントの復習を行った。あと駿台の京大プレ数学も取った。数学は、最低限にも達していないくらいしかやっていないので、出る問題によっては爆死もあり得た。私はもともと数学にはセンスが必要だと思っていたが、ある程度までは演習量でカバーできると最後のほうに気づいたので、数学が嫌いで苦手な人は、時間を要するかもしれないが、腐らず、コツコツやってほしい。(私はできなかった。)
国語
二次の国語は、「世界一わかりやすい京大の国語」を冠模試前にやり、2月に青本15年分をやり、河合塾の京大理系国語テストを受けた。もともと国語は得意だったので、困ることはなかったが、感覚で答案を作るのではなく、答案に必要な全要素を一つ一つ確認しながら組み立てることを意識した。共通テストの国語は、一番ぶれる教科だと思う。私も、12月の模試で120点を取ってしまい、不安が残るまま本番を迎えてしまった。現代文は、過去問や予想問題集を進めながらコツをつかんでいくしかないのかなと思う。古文漢文は、単語や句法を覚えきると不安はなくなる。古文は古文単語330の前の索引、漢文はスゴ技の後ろの暗記ページを使うのがおすすめ。
英語
私は、高2の時に河合塾のONEWEX英語、高3では、佐野先生の京大英語を受講した。英語は河合塾のおかげで、得点源にできたと思う。この京大英語は、テストゼミで、特徴的な京大の英語に早くから慣れることができたので良かった。英単語は、学校で配られたターゲットを高2の間に大体覚えて、春ごろに英検準一の英単語を少しだけやり、7月からはずっと鉄壁をやっていた。英単語帳は何周もやることに意味があるので、単語帳は一冊に絞った方が良いなと思った。鉄壁は絶対にやるべき。英作は、「減点されない英作文」と竹岡の赤の英作の本を軽くやった。共テは、過去問をやったのと、学校でZ会の予想問題集をやったくらい。リスニングは、春のうちから英語のラジオやポッドキャストを帰り道で聞いていたので、困ることはなかった。リスニングは、すぐできるようになるものではないので、早くからラジオを聴いたり、シャドーイングをしたりしておく方が後で楽だと思う。ポッドキャストのVOA Learning Englishを2倍速で聞くのが一番良かった。二次は、青本を12月末から始め、10年分だけやって、終わった後はオープンの過去問を十回分くらいやった。英語は、途中で形式が変わっているので、早めに切り上げて、オープンや実戦の過去問をやるのが良い。細かい採点基準があるので点数が出せるところが良かった。
化学
4月から駿台の山下の化学を受講していた。これは、有機化学だけを一年みっちり教えてもらう講座で、本当におすすめ。この講座では、有機のすべてが詰まったプリントがもらえて、直前に見るものとしても役立った。京大志望の人は、これを取るか、新研究を自分で読み込むかどっちかだと思う。(他の塾でも有機を深くまで教えてくれる講座があるならそれでもいい。)授業以外では、重要問題集を5月から11月にかけて二周終わらせて、新演習を11月から2月にかけて、平衡と有機だけやった。共テは、過去問と駿台の予想問題集をやった。12月くらいまで共テ模試の化学は結構ボロボロだったが、過去問をやり始めてから、めちゃくちゃ伸びたのでそんなに心配しなくて良い。共テの有機は、二次の勉強をしていたら余裕で、理論は過去問で苦手の穴を埋めていく感じ、無機は「福間の無機化学」を丸覚えしたらなんとかなった。やって良かったのは、過去問や予想問題集で知らない知識が出てきたら、ルーズリーフにそれをまとめて、直前に見返す用にしたこと。また、京大無機でないは嘘なので、共テのためにもちゃんと勉強した方が良い。共テ後は、青本を20年分やり、直前講習で取った駿台の京大プレ化学の分厚いテキストの有機と無機、結晶構造の範囲もやった。この講習の授業は正直そんなに良くないが、テキストが役立った。化学は、内容よりも時間に悩まされた。一週間くらい前まで、時間がきつすぎて大焦りだったが、演習量である程度克服できた。
物理
物理は、高2の時は駿台で三幣先生の難関物理を取り、高3でも続けて難関物理を取ったが、週4塾は時間的にも金銭的にも負担だったので、5月には辞めた。三幣先生は、本当に分かりやすかったので、物理の優先順位が高い人にはおすすめ。私は、物理は最初の理解と定義の暗記が一番大切で、そのあとの演習は自分でできるだろうと考えたので、辞める選択をした。7月から8月の前半で、良問の風をやり、8月後半から11月にかけて、名問の森をやった。時間がなくても、良問を飛ばして、名問にいくのではなく、良問を絶対にやった方が良い。共テの勉強としては、化学と同様に、過去問、駿台の予想問題集、プリントまとめを行った。学校で配られたチェック&演習物理も12月にやったが、これは本当にやらない方が良い。この本は、分野別で過去問がまとめられているので、先にやってしまうと、過去問を通しでやったときにちゃんとした点数が出せないので、本当にやらない方が良い。二次は、青本15年分をやり、駿台の京大プレ物理を取った。物理では特に、演習していく中で、疑問に思ったことは、飲み込まず、基礎に戻って解決すべきだと思う。私は、宇宙一分かりやすいシリーズ、ネットサイトの「わかりやすい高校物理の部屋」と「高校物理をあきらめる前に」を愛用していた。また、物理は質問して確実に答えてくれる人を見つけることを強くお勧めする。私は、学校の先生と河合塾の物理のフェローの方にすべての疑問を解決してもらっていた。
地理
京大農学部は、地理の配点がめちゃくちゃ高いのにもかかわらず、私はなぜか全然力を入れて勉強しておらず、12月くらいに痛い目を見たので、夏くらいからコツコツやった方が良い。参考書は村瀬の地理を使っていたが、そこまでおすすめではない。結局、地図帳、教科書、資料集が最強な気がする。地理は、丸覚えではなく、理解しながら知識を詰め込み、それを応用できるようにすることが大切なので、学校の授業もしっかり聞いておくべき。過去問は一応2015年までやったが、センター地理と共テ地理は傾向が違うので、10年以上は遡らず、駿台の予想問題集と、Z会の予想問題集をやった。けれど、地理で高得点は結構運な気がする。
情報
情報も全然傾斜が大きかったが、何をすればよいかわからなかったので、勉強を始めたのは12月からだった。教科書と「ゼロから始める情報Ⅰ」を読み、その問題集をやり、今まで受けた共テ模試の直しをした。本番、知識問題は2問だけだったので、ここまでやる必要はなかったなと思う。学校で冬期補修が組まれるのであれば、それに参加して、プログラミング分野をマスターして、直前に知識を詰め込むくらいで十分だと思う。
最後に
私を信じてくださった松谷先生、金銭の面でも心身の面でも支え続けてくれた両親、励ましあった友人たちに、心から感謝しています。とても周りに恵まれているなと改めて感じました。本当にありがとうございました!これからもよろしくお願いします!
長編!!そして、なんだか正直なことを書いてますね(笑)宣伝しろなんて言ったかな。。。
これをそのまま載せる僕もどうかとは思いますね(笑)ギリギリ合格すすめるな(笑)!
でも、そんなところも彼女らしいですね。かなりいろいろな科目のいろいろな対策について彼女なりに後輩を思って書いてくれていますね。きっと誰かの参考になるんじゃないでしょうか!!他予備校のこともいっぱい書いてますね(笑)
ちなみに、志望校のことは、僕には決定する権利なんかは全くないと思っていて、そういうことはしないのですね。僕がやるのは、ある程度勝算があるかどうかを伝えるのと、考えられる対策を伝えるのと、もし本人がそこを希望するなら頑張れと伝えることだけですね。そうはいっても、結構厳しい勝負だったとは思いますが、共テと二次の本番にばしっと発揮して超えていくなんて心が強かったなあ!!
今度は、チューターとしても生徒のことのサポートしてくれるそうなので、ぜひ生々しい話を聞いてどんどん糧にして欲しいなと思います!